
厚生労働省の統計によると、平成24年度の1年間に約107万件もの労働相談が寄せられています。
人事労務トラブルの代表例としては解雇や残業代不払い、セクハラ・パワハラといったものが上げられますが、近年では、名ばかり管理職の問題や内定取消し、派遣切りなどメディアに大きく報じられるトラブルも生じています。
さらに統計ではいじめや嫌がらせなどの労働相談が増加し、解雇に関する相談が減少するなど、紛争内容は一層多様化しています。
情報化社会になり、従業員一人ひとりの個性が豊かになった現代では、人事労務トラブルは避けて通れないものとなってきています。
対処方法として有効と考えられるのは、労働に関するルールを明確にすることです。
解雇や転勤命令の有効性の基準や就業規則変更の合理性の判断基準等を事前に明らかにし、不要な個別労使紛争は事前に予防します。
経営者や管理監督者は労働者という「人」と協力し、かつ管理していく上で、必要になる労働関係のルールを理解していなければなりません。
企業と労働者との間には時としてトラブルが生じます。そのトラブルを解決するための指針となってくれるのが労働法です。
労働関係の代表的な法律として、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法があり、これらを労働三法と呼びます。
労働法はこの労働三法をはじめとし、労働者派遣法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法などの多数の法律と命令(政令・省令)、通達、判例を総称したものとなります。
まずはこの労働法を知識として身に着け、トラブルが起こった際にまずは冷静になって対応していきましょう。
トラブルになる前に、まずはその予兆がないか気を配りましょう。
労務トラブルが表面化するまでには、まず原因となる原因が必ずあります。その原因をもとに社員の不満や疲労、精神的な苦痛が日々蓄積されていくのです。
そして、それらが限界点を超えたとき、労務トラブルは発生します。
よって、経営者や管理職の立場の人にはトラブルの予兆・サインにどれだけ気づけるかがカギとなってきます。
このトラブルの予兆の例として数値として見えるものとしては、社員の勤怠記録になります。
過重労働や過労死といった労務トラブルはもちろんのこと、うつ病をはじめとしたメンタルヘルスの問題にも社員の働き方は大きく関係しています。
逆にいえば、勤怠管理を徹底していない会社ではトラブルの予兆を見過ごすことにもつながるため、実態が把握できる適切な勤怠管理を行う必要があります。
また、数値では見えない予兆としては、社員の顔色や言動といったものがあげられます。
こちらはハラスメントに関連する予兆といえ、現場の管理職には部下が普段と違う、元気がないといったメンタルケアができるかが求められます。
実例として、年に一度全社員を対象としたカウンセリングを実施している企業もあります。
外部からカウンセラーを招き、一人ひとりに対して会社に対して日々考えていること、悩んでいることを聞き取り調査を実施しています。
このような時間を作ることにより、一人ひとりに対して寄り添った対応が可能となるほか、経営者側からは見えなかった内部の実情が明らかになるケースもあります。
そういった問題点等を一つずつ解消していくことにより、トラブルの防止につながっていきます。
労務トラブルを予防する上で大事な点が事前の丁寧な説明です。
人間は誰しも、先に言えば説明、しかし後から聞くと言い訳と解釈します。
わかりやすい事例が求人や採用の場面です。
最近は人手不足もあり、多くの会社で、実態よりもよく見せた求人内容を掲載するといったことがあります。
本当のことを言ってしまうと応募者が集まらない、内定者が逃げてしまう等といった事情があるからです。
しかし入社した後で「こんな条件聞いていない」という事態が発生してしまえば、それこそ労務トラブルの火種になってしまいます。
このようなトラブルを引き起こす可能性のあるものに対しては、最初から丁寧に説明し理解を求めることが大切といえるでしょう。
法律上も入社時には労働条件の書面での明示が義務付けられています。
双方に誤解がないように書面で条件を確認することは、基本的なことではありますがとても重要なことです。
また、書面で条件を確認するのが大事なのは入社時点だけではありません。
給与制度や人事制度、就業規則を変えたときなどのタイミングで必要に応じて、口頭ではなく書面で説明し、同意を得ておくことが肝となります。
このように、どんなタイミング、どういった書式を用いて日々の労務管理を実行していくのかという再現性のある仕組みを作っていくことも重要です。
例えば、ハラスメントや人間関係のトラブルはたくさんの企業で課題であると考えているものの、実際に社員からハラスメントの疑いが告発された際に、どんな手順で、どういった書式を用い、対応していくかという業務フローができている企業はまだまだ少ないと言えます。
得てして、大企業と違い中小企業では、経理や総務の担当者が人事労務を兼任していることも多いのが実態です。
個人のコミュニケーション能力に頼り切って口頭で何とか乗り切ってしまう会社では、担当者が変わると過去の事例やノウハウが全く活用できずに現場が混乱するという事態になります。
まずはやはり雇用契約書の作成と就業規則の整備をお勧め致します。
「どこから手を付けていいのかわからない」
そのような疑問を解消するために、社会保険労務士へ相談してみませんか?
弊所では中小企業における労務トラブルに対応し、労務相談へサポートを提供しております。
お困りのことがあれば一度ご相談ください。
contents
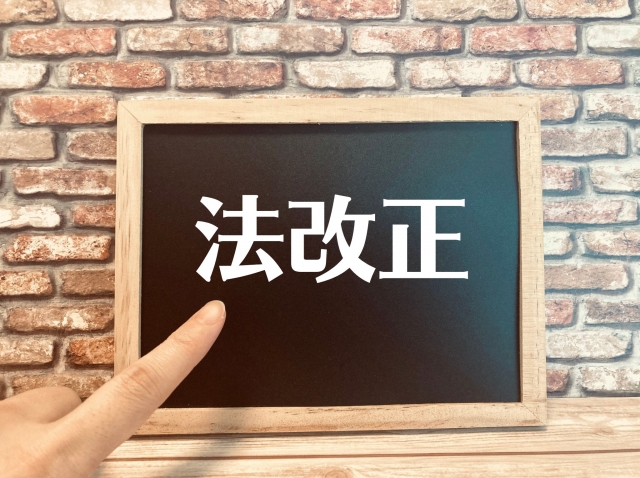
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今日は改正された『育児・介護休業法』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。 &nb…
2024/07/21
コラム

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 今回は『直行で外勤をした後に内勤をした場合のみなし労働時間数の算出』についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合い…
2024/07/14
コラム
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 さて、今日は多様化する福利厚生についてお話させていただければと思います。どうぞ最後までお付き合いいただけますと幸いです。 …
2024/07/05
コラム
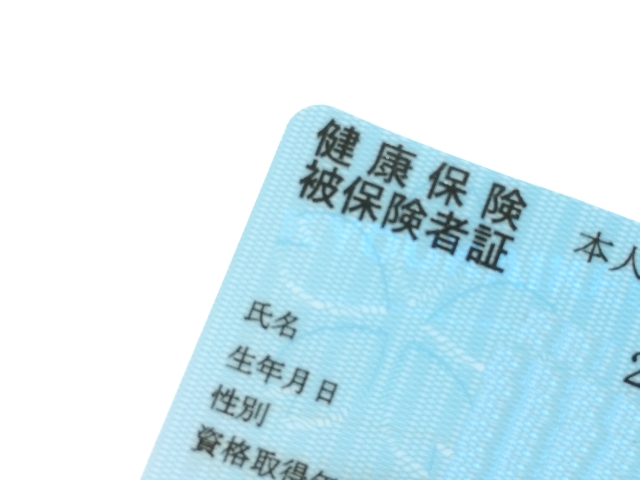
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 さて、本日は令和6年10月からの健康保険・厚生年金保険適用拡大に関する中で短時間労働者の要件について確認させていただければと思います。…
2024/06/27
コラム
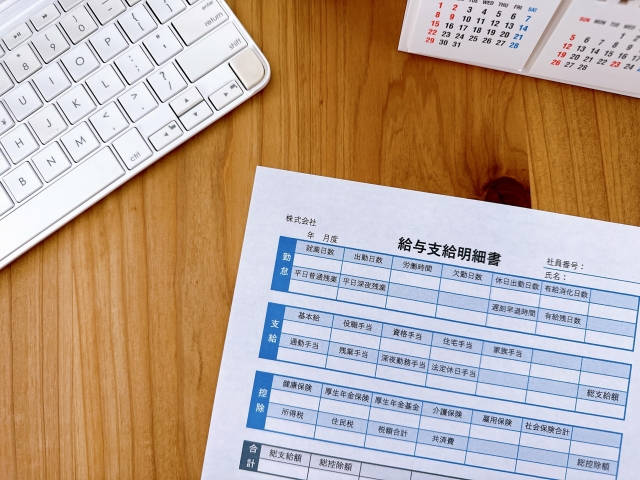
いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 社会保険料や雇用保険料を給与明細に記載する際には一括で控除してもよいのか、という質問に対して今回はお答えしていこうと思います。 どうぞ…
2024/06/11
コラム

いつも大変お世話になっております。社会保険労務士法人きんかです。 連合が賃上げについての集計を公表いたしました。今日はその賃上げ集計についてお話させていただければと思います。 どうぞ最後までお付き合い…
2024/06/04
コラム
Contact
ご質問やご相談などお気軽にご連絡ください。